篠山神社は、明治維新後に旧藩士・藩民によって藩祖有馬


篠山神社は、明治維新後に旧藩士・藩民によって藩祖有馬
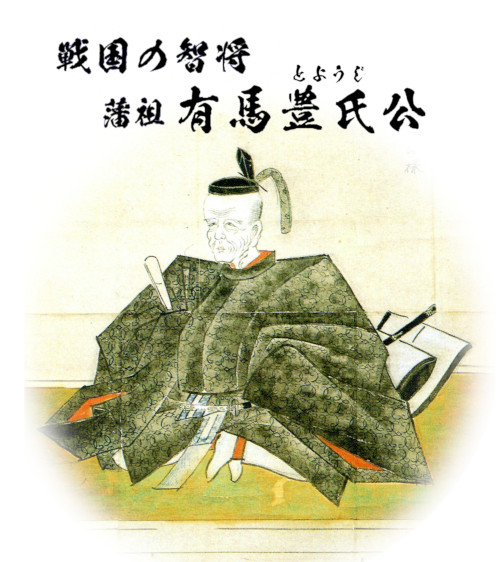
江戸城、駿府城、大阪城等数々の名城の建築修繕を手掛けた築城の名手。茶人でもあり千利休七哲の一人。関ヶ原、大坂の陣、城普請の功により元和七年(一六二一)、丹波福知山6万石から筑後北部21万石に転封され、初代藩主として久留米へ入り、城の修築、城下町整備、藩治に尽力した。
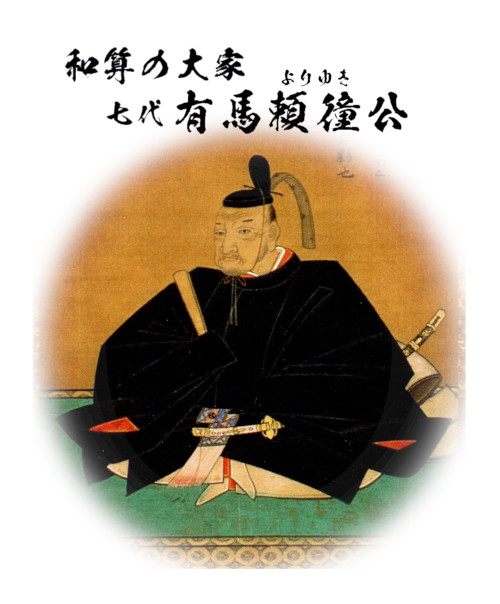
羽犬塚大火災の復興、財政整理等、久留米の吉宗と称される善政で、その治世は五四年にも及んだ。諸学に通じ、とりわけ和算に優れ、我が国の数学の普及と向上発達を大きく進めることとなる『拾?算法』を著した。一郷土史に留まらない数学界の偉人としても知られる。
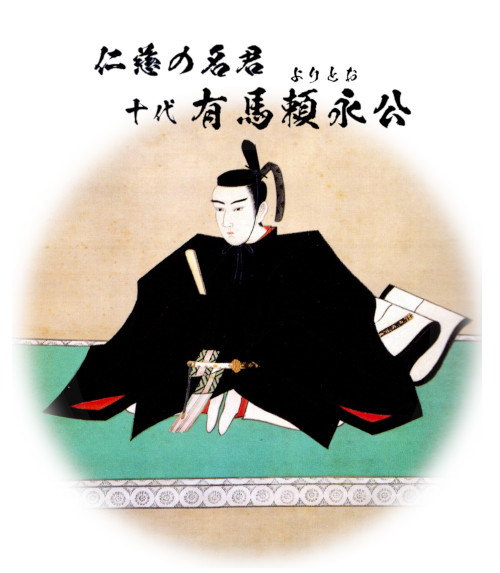
財政再建、軍制の近代化、海防強化などの藩政改革を推進。治世三年だったが仁慈の心篤く民を思う善政に、領民・諸大名が生神様と仰いだ。公を支えた侍講野崎教景の手による治績『感旧涙餘』詩編『思艱斎遺稿』が今に伝えられている。
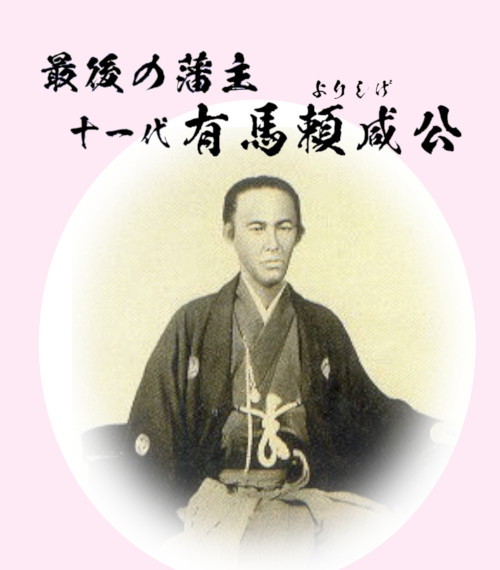
弘化三年、二十歳で十一代藩主となり、以来二十六年、幕末動乱の激浪を耐え抜いた。版籍奉還後、郡県制へ移行し、藩知事となったが間もなく久留米史上最大の難事「辛未の藩難」を迎えることとなった。

農村解放、救貧、女子教育など様々な社会運動に私財を惜しまず情熱的に取り組んだ。国政に進み要職を歴任。近衛第一内閣農林大臣。戦争回避のため和平工作に尽力。中央競馬会理事長として競馬界を導く。創設した中山グランプリは、後に公を顕彰して有馬記念と称された。